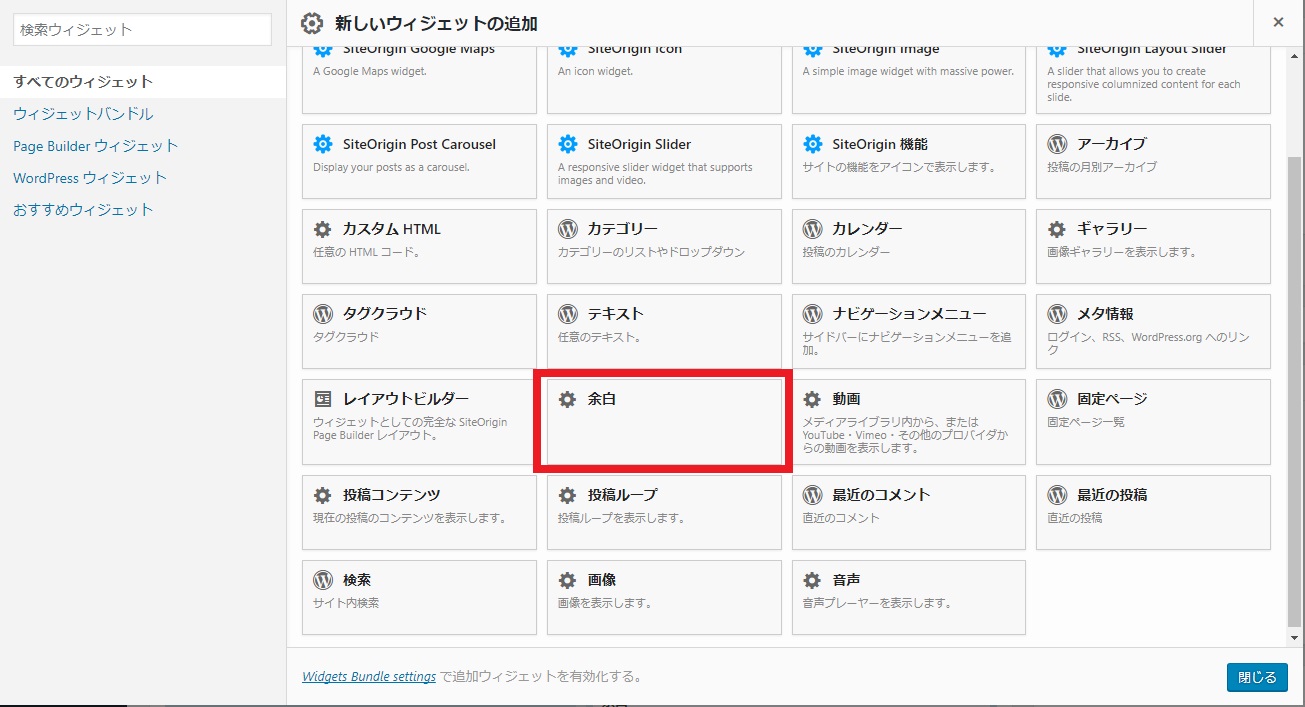アンサンブルコンテストで話題になりやすいのが合図(ザッツ)をどう出すかという問題です。
吹奏楽だと普段は指揮者の先生が合図を出します。

そのため、アンサンブルの時にいざ自分たちだけで演奏してみると、出だしなどの合図の出し方が意外と難しいことに気づきます。
実際に様々なアンサンブルを経験すると、「わかりやすい合図」というのがあります。
今回はそんな、わかりやすい合図とそのために有効な練習方法について書いてみたいと思います。
練習編
合図を出すための練習は、次の流れをイメージして行ってみると効果的です。
自分が苦手なところを集中的にやってみてください。
1.脳で確認
2.身体で確認
3.楽器で確認
1.脳でテンポをつかむ。テンポ感の共有
身体で合図を出す前に、まずは頭の中でテンポをしっかりと確認してみましょう。
これは合図だけでなく演奏自体にも大切ですが、曲を吹き始める前や、テンポが変化していくところでは、テンポをメンバーで共有しておくことが大切です。
テンポがしっかりと共有できると合図も自然と出しやすくなります。
・練習方法
メンバー全員でメトロノームに合わせてカウント(または手拍子や足踏み)をする
メトロノームを鳴らしながら合図を出す練習をする
・目的
テンポ感の共有
2.指揮(手)で合図してみる。
楽器を通して合図を出す前に、指揮者のように手で出してみましょう。

その際に、曲が始まる1拍目の前の拍(4拍子の4拍目。予備拍といいます。)をしっかりとテンポで出せるように気を付けてみましょう。
・練習方法
合図を出す人は楽器を構えずに指揮をして曲を始める
上の方法で曲の出だしのみ何回か繰り返して練習する
・目的
自分の合図で音が出る感覚をつかむ
共有したテンポ感を身体(手)を通して出せるようにする
3.楽器を通してテンポを出す
ここまでできたらいよいよ、次は楽器をもって合図を出してみましょう。

この時に気を付けたいことは手で出している時よりもテンポを共有するための点(ポイント)が身体から離れているということです。
例えばトランペットの場合、楽器のベルの部分にポイントがあります。そのポイントを意識して練習してみてください。
☆このポイントは各楽器を構えた際、身体から一番離れているところにあります。
・練習方法
楽器を構えてテンポを出してみる
・目的
楽器を経由してもテンポが出せるようになる
楽器のポイント(拍を出す点)がどこかを理解する
コツ編
1.動き方
基本はタテの動きで大丈夫です。人によっては指揮のように振り子のように動いて合図を出すこともあります。
・動きすぎないように気を付けてください。
2.どのくらい動くのか
吹き口部分の動きは2~3㎝で十分です。楽器を構えてみるとわかりますが、吹き口は2~3㎝しか動かさなくても、ベルの部分は5~10㎝程度動くため、十分に拍がわかります。
3.動く速さ
曲のテンポにもよりますが、特に速い曲の場合は、点を出すためのポイントを意識して素早く動かしましょう。
4.自分もブレスがしやすいように動く
実際に演奏をはじめるので、自分がブレスが吸いやすいような動き方で合図を出してください。必要以上に固くなったり動きすぎる必要はありません。
そうすることによって他のメンバーにとっても息の吸いやすい合図になります。
まとめ
アンサンブルの時に出す合図の出し方とコツについてまとめてみました。まとめると、
・合図は、脳→手(身体)→楽器の順で練習する
・動きは最小限で素早く動く
・ブレスの取りやすい動きを心掛ける
ということになります。
おそらく合図を出すメンバーは上級生やパートリーダーが多いと思います。しっかりとした合図は演奏にメリハリを与えます。
自信をもって出せるようになり、アンサンブルを引っ張っていけるようになってくださいね。
最後にアンサンブルの合図の参考に動画をひとつ貼っておくので、参考にしてみてください。
吹奏楽部にとって夏の吹奏楽コンクールとの対極にあるもの。 それが冬のアンサンブルコンテスト。 できることなら金管5重奏、木管5重奏、サックス4重奏などオリジナルの編成で出場できればいいけれど、学校の編成の事情などで近年増えてい[…]