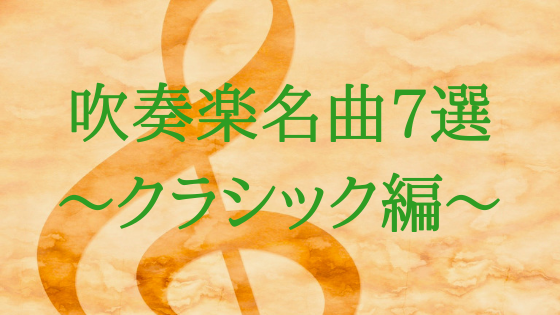2019年4月20日。知り合いに連れられてとあるピアノコンサートに足を運んだ。
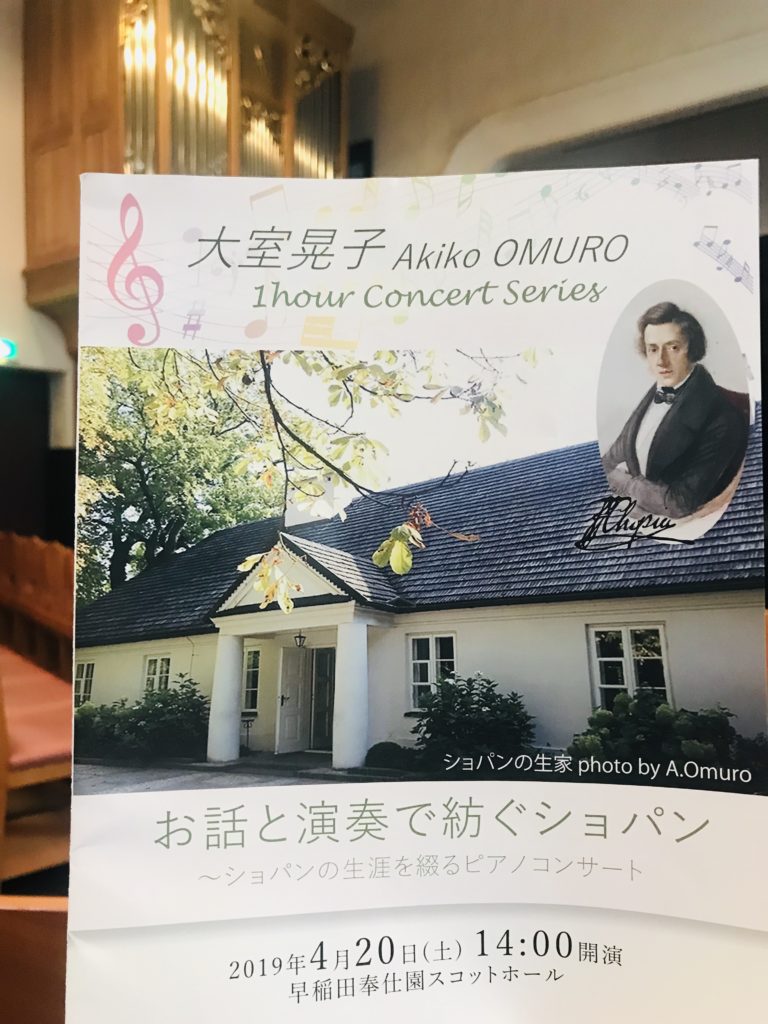
副題にある通り「ショパンの生涯」に焦点を当てて、話も交えながら演奏していく形式のコンサート。
ピアノのソロは何度となく聴く機会があったが、その中でもトップクラスに感動した演奏会だった。
恥ずかしい話、それまでショパンという作曲家についてあまり知らなかった。そんな私が、コンサートを聴き終えた頃には、自ずとショパンという一人の人間に感情移入していた。
今回はこのコンサートを再現するような形で、「ショパンについて」記事にしておきたいと思う。
この記事は、コンサートで素晴らしいプログラミング、演奏、お話をお聞かせくださったピアニスト大室晃子氏に最大級のリスペクトをもって、時にその言葉も引用させていただきながら書き残しておきます。
幼少期〜才能あふれる少年
コンサートはこの曲で幕をあけた。
ポロネーズ ト短調 遺作
これは7歳の頃に書いたフレデリック・ショパンの作品。
「遺作」となっているのは生前彼がこの曲の出版を望んでいなかったものを、その友人がもったいないと出版したからだが、この作品からも小さい頃からすでに彼が音楽的な才能を発揮していたことがわかる。
若きショパンの挫折
練習曲 ハ短調「革命」 作品10−12
ポーランドで生まれ育ったショパンだったが、ショパンの曲の中でも特に有名なこの曲。別名「革命のエチュード」
幼い頃からその才能を発揮し、すでに演奏家としても作曲家としても成功をおさめていた若きショパンはさらに活躍の場を広げようと1830年20歳の時に「音楽の都」ウィーンを目指した。
ちなみに、この時に母国ポーランドの土を入れた銀の杯を餞別にもらっているが、これを最後に彼がポーランドの土を踏むことは二度となかった。
1830年と言えば、世は古典派とロマン派の境目。
3年前の1827年までは世紀の大音楽家L.v.ベートーヴェンが、2年前の1828年までは歌曲王シューベルトが生きており活躍していた当時のウィーンでは、残念なことにショパンの作風が日の目を見ることはなかった。
この時代はショパンの生涯の中でも「魔の時代」「無為の時代」と呼ばれ、ショパンはわずか8ヶ月でこの街をあとにし「芸術の都」フランスパリへ向かうことになる。
その頃、パリではある事件が起きていた。
ヴィクトル・ユゴーの「レ・ミゼラブル」でも取り上げられる「7月革命」である。
パリへ向かう道中、祖国ポーランドの反乱がロシアによって鎮圧されたという知らせを受けたショパンは
「神よ。なぜあなたはロシア軍にポーランドの鎮圧をゆるしたのですか」
「それともあなたはロシア人だったのですか」
とひどくショックを受けたという。そしてその思いを込めて作曲されたのがこの有名な「革命のエチュード」(1831年頃作曲)だった。
ちなみにこの曲、今では「革命」をイメージしたものではないとされる説が有力だが、作曲された時代背景を考えてみてもショパンの心には少なからず影響していたのではないかと思う。
パリ時代〜花ひらく才能と祖国
ポーランドからウィーン、そしてパリへと移り住んだショパン。
この頃、ポーランド反乱の失敗を受けて、母国ポーランドの知的階層も多くがパリに亡命していた。
サロン文化を好んだショパン
そんな彼らは、同郷の才能ある芸術家であるショパンをパトロンとして支えたが、ショパンにとっても母国語で話ができる数少ない特別な存在でもあった。
そんな彼らとの交流が行われたのが当時の「サロン」で、ショパン自身もコンサートなどの公開演奏会よりもサロンの場を好んでいたという。
そしてそんなパリ時代、1833年に作曲されその翌年1834年に出版されたショパン最初のワルツ作品がこの曲。
華麗なる大円舞曲 変ホ長調 作品18
ウィーン時代の影響を受け、様々な小さなワルツが散りばめられる「ウィンナー・ワルツ」の形式を踏まえて書かれたこの作品は、さながら映画の場面を様々に切り取るカメラワークのような効果を聴く人に与えてくれる。
サロンでみんなが集まって踊っている様子。
そこからカメラが切り替わり隣の部屋へ。そこではひと組のカップルがダンスをしている。
さらに切り替わって別の部屋でもうひと組のカップルが踊っている。
その2組のカップルが宮殿の大階段を並んで降りきて、
最後には再び大団円となる。
大室晃子(ピアニスト)氏の言葉より
この曲は、その華やかな演奏効果もあいまってパリの人々に受け入れられた。
そうして次第に活躍し始めたショパンは、1836年、幼馴染のマリアに恋をしプロポーズをしている。この申し出、一度は受け入れられたものの彼女の両親の反対にあい最終的に二人は自然消滅してしまう。
ショパンはマリアからもらったバラの花、そしてマリアとその母からの手紙を1つの大きな紙包みにまとめ、その上に「我が哀しみ Moja bieda」と書いた。
ポーランドへの思いと作品
バラード第1番 ト短調 作品23
ウィンナー・ワルツのように他国の音楽を吸収して作品を生み出したショパンだが、自国ポーランドの音楽に対しても意欲的な作品を多く残している。
その一つが「バラード」である。
ショパンと同時代に生き、パリで交流もあったポーランドの詩人アダム・ミツキェヴィッチの詩に感化され、ショパンは全部で4つのバラードを残した。
それぞれの曲がミツキヴィッチの詩に関連づけられているとされるが、ショパン自身具体的な詩との繋がりは明らかにしていない。そして、中でも特に有名なのがこの「バラード 第1番」で1836年(26歳の時)に出版されている。
ちなみに、「バラード」とはもともと「物語(譚詩)」を指す言葉で、もともと歌曲の一種だったバラードを一つのドラマティックなピアノ曲のジャンルとして確立したのがこのショパンの作品群である。
ジョルジュ・サンドとの出会い
幼馴染と失恋したショパンだったが、とあるパーティーでフランスの作家ジョルジュ・サンドと出会い恋仲になる。
“ジョルジュ・サンド”というのはペンネームで、男性の名前なのだが、実際は女性だった。当時にしては非常に珍しく、経済的、社会的に独立していた彼女はフェミニストのはしりとしても有名である。
そしてショパンがサンドと交際していた1839年から1846年の7年間の期間、夏になるとパリから車で3時間ほど南下した街にあって、サンドが少女時代を過ごした家でもある「ノアンの館」でショパンは創作活動を行うようになる。
パリの喧騒から離れて創作に専念できたこの地はショパンにとって絶好のアトリエで、この時期に残された作品はショパンの全作品のうちなんと3分の2にも及んでいる。
この「即興曲第3番」もそんなショパンの最も充実した創作期に残された一曲。(1843年出版)
即興曲第3番 変ト長調 作品51
変ト長調(GsDur)で書かれた曲は、柔らかな雰囲気を感じさせるあたたかな作品で、パリ時代の華やかな作品とはまた違ったショパンの優しい人柄を伝えてくれている。
もともと病気がちだったショパンだったが、サンドと別れてパリに戻ってからはますます病気が悪化し、演奏活動もままならなくなっていった。
変化する作風と晩年の傑作
ショパンの作風は、
前期:パリ時代サロン向けの作品
中期:ポーランドを思う作品
と変化していくが、多くの作曲家がそうであったようにショパンもまた晩年にかけて数こそ少ないが「内省的な作品」を残すようになる。
幻想ポロネーズ 変イ長調 作品61
この曲もそんな最晩年1846年(ショパン36歳)に出版された傑作のひとつ。今回のコンサートでも最後を飾っていた。
ショパンの作品の中では比較的長い曲に分類されるこの曲は彼自身の経験、
祖国ポーランドの鎮圧やウィーンでの挫折、といった「出来事」
幼少の頃の幸せな記憶、喜び、悲しみといった「感情」
戦争や恋、病といった自分ではどうしようもできないことへの「叫び」
など、まさにショパンの人生を走馬灯のように今に生きる私たちにも訴えかけてくる。
のちにあの大ピアニストであり作曲家として名高いフランツ・リストもこの曲をして
「この痛ましい幻影は芸術の域を超えている」
とその完成度を評していることからも時代を超えてこの曲がショパンを伝えていることがわかる。
ショパンの死とそのスタイル
パリで行われた葬儀
1849年。39歳の若さでショパンはこの世を去った。
死因は明らかになっていないが「肺結核」とする説が最も有力で、生涯に渡って残した作品は作品番号があるものが74曲、作品番号のないものまで含めると約130曲に及ぶ。
そして、そのほとんどが「ピアノの詩人」の名に相応しくピアノのために書かれている。
すでに時の人となっていた彼の葬儀はパリの街をあげて盛大に行われ、棺の彼の遺体の上には彼がポーランドを出る時に餞別として送られた銀の杯に入った祖国の土がかけられたという。
また、
「心臓だけでもポーランドに帰りたい」
というショパン自身の遺言によってその心臓は、姉によって祖国に持ち帰られワルシャワの聖十字架教会の柱の奥深くに今でも埋まっている。
スタイルとその魅力
ショパンの生き方は生涯を通して徹底している。
同年に生まれた作曲家にロベルト・シューマンがいるが、彼は感情や出来事をそのまま作品に残すタイプの作曲家だった。
その一方でショパンは、一時の感情に流されることなくひとつの出来事を経験したとしても、それを昇華して音楽的に完成させることを重視した作曲家だった。
音楽で何かを端的に表現する「標題音楽」ではなく、純粋に「絶対音楽」として作品を作り続ける姿勢を取っている。
それも「ピアノ」という楽器の可能性だけをただひたすらに追求して。
彼の39年という短い人生を考えると、もし彼がピアノ曲以外にもその作曲の幅を広げていたら、今ほど多くのピアノ作品は生まれてなかったのではないだろうか。
しかし、徹底して「音楽」「ピアノ」に向き合っている一方で、
祖国の敗戦に激情し、女性との恋愛に苦しみ、死んでなお祖国へ帰りたいと願う…
そんなごく人間らしいエピソードがある。
病気がちということもありきっと順風満帆なだけの人生ではなかったと思う。
でも、そんな全ての出来事を自分の経験にし、人間的に成長し、最後は音楽を通して表現する。
そんな音楽に対して一切妥協のない真摯な姿勢が今なおピアニストを中心にその心を掴んで話さないショパンの魅力なのかもしれない。