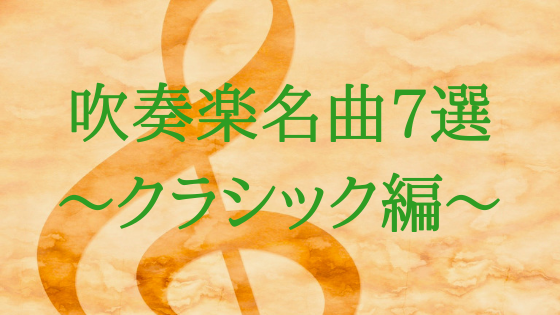さてさて2019年4月。かなり今更感はありますが観てきました「ボヘミアン・ラプソディ」。

クイーンは小学校時代からの親友が好きだったこともあり比較的小さい頃から聴く機会はありました。
そんなクイーンですが、今回ボヘミアン・ラプソディを観て改めて「アーティスト」としてのすごさを感じました。せっかくこんな名前のブログを書いていることもあるので、文章にしておきたいと思います。
オープニングシーンの不思議
映画最初のフレディが目覚め、映画の最終的なステージでもあるライブ・エイドに向かうシーン。

このシーンは映画の最後のシーンと繋がっている場面なのですが、最初見た瞬間からどことなくある種の“違和感”がありました。それが、
「フレディ-孤独」
ということ。映画のラストシーンでは当然クイーンのメンバーと共にステージに出て行くのですが、冒頭のシーンはあくまでもフレディのみ。どこか意図的な印象を受けました。
フレディ本人の表情すら見えないその演出は、どこか俯瞰しているような(それこそクイーンのメンバーが観たフレディの背中?)遠い印象を覚えます。
これから映画に引き込むためのイントロダクション的な意味で遠い視点なのか、それとも何か違う意図があるのか…DVDが発売されたら最後のシーンと見比べてみたいと思います。
オペラに傾倒するフレディ
「クイーン」は言わずと知れたロック・バンドですが、フレディは単なる「ロック」の枠組みではなく音楽的な高みを常に目指していることがわかります。
それをわかりやすく教えてくれたのが、フレディのオペラに対する知識。
実際にフレディはスペインの有名オペラ歌手モンセラート・カバリェと共演しており、その出来事だけで見てもジャンルを超えたアーティストだと感じさせてくれます。
また映画の中、事務所でレコード会社重役レイ・フォスターに向かってフレディが放つ
オペラのように熱狂的に…
という言葉からもフレディが単なるロックの枠組みではなくエンターテイナーとしてより高次元な場所を目指していることが伝わってきました。
また、映画の中では3曲ほど有名オペラのアリア(オペラにおいて歌手が見せ場的に歌う曲)が挿入されていますが、どの選曲も秀逸でそれぞれのアリアにもやはり意図があったように思えてなりません。
プロポーズのシーン/ある晴れた日に(オペラ『蝶々夫人』より)
フレディがメアリーにプロポーズしたシーンで流れていたアリアがプッチーニのオペラ『蝶々夫人』の「ある晴れた日に」。日本を舞台に悲しい運命を負った若い妻(蝶々夫人)が歌う曲です。
こちらの動画、歌っているのは伝説のオペラ歌手マリア・カラス。実はこのマリア・カラス、映画の冒頭でフレディが自分の部屋を出て行く時に写っているポスターの人でもあります。
本来であれば結婚という幸せなはずのこのシーンに、アメリカに戻り帰ってこないアメリカ人夫を思い日本の若妻が「きっと夫は帰ってくるの」と歌うアリアが流れている。
決して幸せだけとは言えない二人の将来を暗示しているように感じます。
事務所のシーン/ハバネラ(オペラ『カルメン』より)
先ほどのレイ・フォスターに「ボヘミアン・ラプソディ」の価値をクイーンが訴えていた場面で、フレディがかけたレコードのオペラアリアです。
オペラを知らない人でも一度は耳にしたことがあるのではないかというくらい有名なこの曲。
歌の中身も
「愛はボヘミアンの子。決して、決して規則なんて知らない」と、まるでそのシーンを象徴するかのような歌詞が使われています。この曲を歌うカルメンもオペラではボヘミアン(ジプシー)です。
すれ違うシーン/お聞きください王子様(オペラ『トゥーランドット』より)
フレディが隣の家に住むメアリーに電話しランプをカチカチするシーンで流れたオペラアリアです。
ここでは先ほどの『蝶々夫人』同様プッチーニの代表作(かつ遺作)である『トゥーランドット』から「 お聞き下さい、王子様」という曲が流れていました。
この曲はヒロインであるトゥーランドット姫に思いを寄せる王子に、密かに恋い焦がれる召使いのリューが歌うオペラ屈指の有名なアリアで、「このままでは私の心は砕けてしまいます」と叶わぬ恋心を訴えています。
フレディが無邪気な好意で「乾杯しよう」と言うのに対して、電話越しのメアリーが言葉だけを合わせてグラスは持っていなかったシーン。一つの恋の儚さを感じました。
オペラアリアに共通すること
この3つのオペラアリアに共通しているのは、どの歌も歌っている本人が「孤独に死を迎えた」ということです。
- 蝶々夫人は帰らぬ夫を待ち孤独(その後自殺)
- カルメンも愛に生き孤独(最後は殺される)
- リューも王子の愛に生き孤独(最後は自殺)
そして、フレディもどこかで「孤独」を抱え続け最終的には病で亡くなる。オペラアリアから見ても、それぞれの選曲に明確な共通点を見ることができます。
クイーン=女
もう一つこのオペラアリアを並べて気づいたことがあります。それが、全て女性ソプラノのアリアということ。もちろんアリアにはテノールやバリトンなど男性のものもありますが、映画で使われるのは全て女性のアリア。
そして、フレディもどこか「女性的」だと思います。
「クイーン(Queen)」という名前も“女王”を表し、男性4人のグループなのに不思議だなと思っていましたが、このことに気づいてなんとなく腑に落ちました。やはりフレディ自身もユニセックスな部分があると思います。
これは私自身の持論なのですが、根本的に男性には「女性に対しての憧れ」みたいなものがあり、その点からもフレディやこの映画の思想に共感した部分がありました。
ゲイという秀でた才能
フレディ・マーキュリーは同性愛者です。今では当たり前のこととして受け入れられますが、彼が生きた時代にはとても生きづらい環境だったことは想像に難くありません。
映画の中でも随所にその生きづらさや社会背景が描かれていましたが、特に記者会見でフレディが記者に詰問されるシーンで感じたことが、
一人の人間としての俺を見てくれ
というフレディのスタンス。
人間、アーティストを見るときには生まれや境遇など、どうしてもその背景を透かして見てしまうことがありますが、フレディはそんなこと全部関係ない、「俺の生き様、音楽だけを見てくれ」と言っているように感じました。
歴史に名を残す同性愛者
クラシック音楽の世界には歴史に名を残した同性愛者が多くいます。
- 恋人であった甥に作品を捧げたチャイコフスキー
- フランスの代表的な作曲家プーランク
- ラプソディーインブルーのガーシュイン
他にも実際には(時代的な難しさもあり)公表こそしていないものの偉大な作曲家の多くが同性愛者だった可能性があります。
「愛」を固定観念を捨てて考えたとき、異性ではなく同性を愛する人がいることもなんら不思議なことではないかなと思います。
そして、ある意味で女性的な感覚も持ち合わせる同性愛者は人間的に感性が豊かで「芸術」の分野においても秀でた才能を発揮していたのではないかとも思います。
フレディ・マーキュリーもそういった多くの偉大な芸術家と同様、後世に受け継がれる偉大なアーティストであることは間違いありません。
偉大な音楽家との共通点
ここまでにもクラシック音楽との関わりを見てとれるフレディですが、他にも音楽家として偉大な作曲家との共通点を感じます。
バッハとの共通点

「音楽の父」として有名なバッハですが、クラシックの基礎を作ったバッハと、今となっては「ロックの当たり前」を多く作ったフレディは似ています。
ベートーヴェンとの共通点

『ボヘミアン・ラプソディ』とベートーヴェンの『交響曲第九番(歓喜の歌)』は似ています。
映画の中で、ボヘミアン・ラプソディに対して「6分なんて長すぎる!!」とレコード会社に言われるシーンがありますが、今となってはそんなにおかしな話でもなく、クイーンがロックの常識を覆したと言えます。
ベートーヴェンの第九も上演時間1時間とそれまでのクラシック音楽の常識から考えると「長すぎる!!」交響曲でしたが、ベートーヴェンはその常識を覆して新しい常識を民衆に対して確立しました。
そして、フレディとベートーヴェンも「生涯結婚することなく独身」だったという点で共通しています。
チャイコフスキーとの共通点

先ほども少し出てきましたが、フレディもチャイコフスキーも同性愛者という点で共通しています。
そして、もう一つ共通するのがどちらも「メロディーメーカー」だということ。
優れた作曲家の才能の一つに「耳に残るメロディーを書ける」というものがありますが、二人ともその才能に秀でていると感じます。
ジョン・ケージとの共通点

現代音楽の大家、ジョン・ケージとも共通点があります。それは「新しい響きを求めた」という点。
映画内でクイーンの最初のアルバム作成シーンでマイクを振ってみたり、ドラムに何か撒いてみたり…と奇抜な音を探していたシーンを見て、発想にとらわれず常に前衛的な音楽を生み出したジョン・ケージを思い浮かべました。
ズービン・メータとの共通点

ズービン・メータはインド出身の世界的指揮者ですが、彼もフレディと同じゾロアスター教の信者です。宗教と芸術の共通点といえばユダヤ教が有名ですが、フレディのバックボーンであるゾロアスター教(拝火教)にも有名な人がいます。
映画の中でフレディが彼の父とわかり合う言葉として「善き考え、善き言葉、善き行い」という言葉が出てきますが、これもゾロアスター教の「善思、善語、善行」という基本的な教えを説いています。
フレディも少なからずこの思想に影響は受けていたのかなと考えられますね。
エンターテイナーとしてのフレディ
ここまでオペラアリアで紐解いてみたり、クラシックの作曲家になぞらえてみたりと私なりに映画ボヘミアン・ラプソディについて書いてみましたが、当初から言われていた通り「ラスト21分」に向けて非常にドラマティックに演出されていたなと改めて思います。
もちろん、ライブ・エイドのコンサートの再現も素晴らしかったですが、それよりも印象的だったのが、その少し前にあったフレディがクイーンのメンバーにエイズを告白するシーン。
死を迎え入れたフレディがエイズを告白し「エンターテイナーであり続ける」と言った場面。アーティストとしての凄まじい「生き様」を見ました。
ベートーヴェンも難聴や病に立ち向かいながら最後まで芸術家であり続けましたが、フレディも同じだなと。
人間の生き様は死に際に最も濃く現れると感じます。
そしてその告白を受けてのライブ・エイドでのフレディのパフォーマンス。エンターテイナーとして「向こう側に行った」パフォーマンスが観る人を揺さぶるのはある意味必然にも感じました。
もうこんな人は出てこない?
ロックというジャンルを超越したエンターテイナーであるフレディ・マーキュリー。今回こうして記事にすればするほど、人間的な奥行きを感じます。
それと同時に生で見てみたかったな。とも。
彼亡き今、ライブで観ることは叶いませんが、今回こうして自伝的な映画ボヘミアン・ラプソディを通してその人となりを知ることができたのはとてもいい経験になりました。
クラシック音楽はバッハ以降、バッハの音楽をいかにして崩すかを考えていた。
という話を聞いたことがあります。
要するにクラシック音楽はバッハの時代に音楽的にも理論的にも完成しており、それ以降はバッハの音楽をいかに崩すかだった。ということなのですが、フレディの音楽もある意味ではロックの完成形のように感じました。
そして、その唯一無二の音楽を超えることはそうできることではありません。
最後のライブ・エイドのシーンで歌われた『ボヘミアン・ラプソディ』、全てを乗り越えた彼が歌った『ウィーウィルロックユー』。
まさに魂が揺さぶられるようなパフォーマンスはフレディの持つエネルギーそのもの。最近のポップミュージックで、私は今回ほど心揺さぶられたことは残念ながらありません。
バッハ以降の作曲家がそうであったように、彼らを超えることはきっと容易ではないのだと思います。
まとめ〜ボヘミアンなラプソディ
クイーンを代表する楽曲の曲名であり、この映画のタイトルでもある『ボヘミアン・ラプソディ』。
日本語に訳すとすれば
世間の習慣など無視して放浪的な生活をする人による狂詩曲
題名だけで見れば、クラシック音楽の曲名としても通用すると思いますし、このタイトルはそのまま
クイーンの在り方、フレディ・マーキュリーの在り方、そしてその「叫び声」を表しているように思えてなりません。
映画を観終わって、今こうして記事に改めて思うことは、
フレディの生き方そのものが「ボヘミアン」な「ラプソディ」だな、と。
クラシックにも造詣が深く、エンターテイナーとしての在り方を追求し続けた「フレディ」の姿から今に生きる私たちが教えられることは、たくさんあるように感じます。